|
■カテゴリー |
ご相談内容(クリックで回答を表示できます。) |
|
|
|
|
|
|
■不動産相続 |
Q1.私たち夫婦には子供がなく、また両親も死亡しています。私の財産は妻だけが相続するものだと思っていました。しかし、妻だけではなく私の兄弟姉妹にも相続権があると聞きました。本当ですか? |
|
|
|
|
|
|
■遺言書
相続 |
Q2.私は、長年献身的に世話をしてくれた長男の嫁に、遺産の一部を与えたいと考えています。そのために遺言書を作成しようと思っています。遺言書を作るにはどうすればよいのでしょうか。 |
|
|
Q3.遺言書を作っておいたほうがよいのは、どのようなケースですか? |
|
|
|
|
|
|
■会社設立 |
Q4. 会社を設立したいのですが、どのような種類の会社があるのでしょうか?また「新会社法」のスタートで、どのような点が変わったのでしょうか? |
|
|
|
|
|
|
■トラブル |
Q5.借金を整理したいのですが、どういった方法があるのですか? |
|
|
Q6.借金の相談をしたいのですが、なにを聞かれるのですか? |
|
|
Q7.借金は150万円ほどですが、自己破産できますか? |
|
|
Q8.自己破産をしたら家族に知れますか? |
|
|
Q9.自己破産をすると戸籍や住民票などに記載されますか? |
|
|
|
|
|
|
■建設業
許可申請 |
Q10.現在建設業を営んでいますが、この度「建設業許可」を受けたいと思います。そのためには、いくつかの「許可要件」があると聞きました。それはどのようなものでしょうか。 |
|
|
|
|
|
|
■就業規則 |
Q11.就業規則とはどういうものですか。 |
|
|
Q12.就業規則とはどういう場合に作成するのですか。 |
|
|
Q13.就業規則には何を記載しなければなりませんか。 |
|
|
|
|
|
|
■助成金 |
Q14.助成金とは? |
|
|
Q15.どんな助成金がありますか。 |
|
|
Q16.助成金をもらうには何か条件があるのですか。 |
|
|
|
|
|
|
■国民年金 |
Q17.
私は、昭和21年4月生まれです。夫はサラリーマンです。
結婚は昭和42年9月で その時 夫は既に厚生年金に加入していました。当時、国民年金に加入しておらず 昭和61年4月からは第3号被保険者ということで保険料は納付しておりません。もうすぐ60歳になります。私は国民年金がもらえますか。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
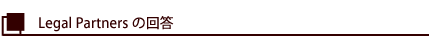 |
|
|
 |
|
Q1.
私たち夫婦には子供がなく、また両親も死亡しています。私の財産は妻だけが相続するものだと思っていました。しかし、妻だけではなく私の兄弟姉妹にも相続権があると聞きました。本当ですか? |
|
 |
A1.
お子さんがおられない方は、死亡したら妻だけでなく、兄弟姉妹にも相続権があります。
あなたの両親が健在であれば相続権が親と妻ですが、もし両親共になくなっておられると あなたの妻だけではなく、あなたの兄弟姉妹にも相続権があるのです。兄弟姉妹が既に死亡していれば、甥姪までその相続権があります。
この相続権の割合は奥さんが3/4、兄弟姉妹が1/4になります。兄弟姉妹が数人いれば この1/4を兄弟姉妹の人数で割ります。
ですから、あなたが亡くなられた場合には妻だけでなく、あなたの兄弟姉妹を含めて相続をせざるを得ません。この兄弟姉妹にも相続権が発生することをご存知無い方が意外とおられます。奥さんだけにすべてを相続させたいのであれば、遺言書を作成することをお勧めいたします。
また、兄弟姉妹には「遺留分」という権利がありませんので、あなたが遺言書を作成されたら 兄弟姉妹から相続財産に対して主張される恐れはなくなります。 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに詳しく知りたい方は お気軽にお問い合わせくださいませ。
 |
|
|
 |
|
Q4.
会社を設立したいのですが、どのような種類の会社があるのでしょうか?
また「新会社法」のスタートで、どのような点が変わったのでしょうか?
|
|
 |
A4.
まず、平成18年5月1日の「新会社法」の施行に伴い、今後は「有限会社」の設立は出来なくなり、現在の「有限会社」はそのまま「特例有限会社」として存続するこになりました。
そこで今後会社を設立する場合は、下記の4種類の中から選択することとなります。
1.株式会社 2.合同会社 3.合名会社 4.合資会社
上記の中でもやはり一番一般的なものは「株式会社の設立」だと思います。
今回の改正では「株式会社の設立」に関して大幅にその要件が緩和されましたので簡単にご紹介しておきます。
1.最低資本金制度の撤廃 (資本金1円でも可)
2.役員・監査役の員数規制の撤廃 (役員1名でも可)
3.類似商号の規制 原則廃止
4.払い込みの保管金証明書が不要に! 代表者の払込証明でOK
(通帳のコピーでも可)
5.株式譲渡制限会社にした場合、定款に記載することで役員の任期を10年
まで延長することが出来る。
この他にもいくつかの変更点もありますが、「株式会社の設立・運営」が以前に比べて格段に容易になったといえるでしょう。
などの 色々なメリット・デメリットを勘案して、会社を設立すべきです。 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに詳しく知りたい方は お気軽にお問い合わせくださいませ。
 |
|
|
 |
|
Q7.
借金は150万円ほどですが、自己破産できますか? |
|
 |
A7.
あなたの持てる支払い能力のすべてをもってしても借金が払えないなら、自己破産できる場合もあります。
たとえば、あなたが多額の借金を抱えていて、持っている財産すべてを処分してお金にかえても借金を完済できないときは、破産状態にあるといえるでしょう。
しかし、将来的に借金を返せる見込みがあるなら、いま自己破産をする必要はありません。債務整理をして、自己破産せずに立ち直ることが大切です。
将来的にも借金を返せる見込みがない場合は
(扶養家族がいて生活に全く余裕が無い・病気やケガ、高齢などの理由で当分の間就業できない場合など)
いち早く生活を立て直すことを考えなければならないので、たとえ150万円でも自己破産することが認められるでしょう。 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Q8.
自己破産をしたら家族に知れますか? |
|
 |
A8.
同居の家族に内緒で自己破産するのは難しいでしょう。
自己破産申し立ての際、「家計全体の状況」を裁判所に聞かれますので ご本人はもちろん、同居の家族の給与明細・源泉徴収票などを提出しなければなりません。
むしろ、人生をやり直すために自己破産手続きを選んだことを家族に説明し 納得してもらい、協力を仰ぐことが大切です。 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに詳しく知りたい方は お気軽にお問い合わせくださいませ。
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに詳しく知りたい方は お気軽にお問い合わせくださいませ。
 |
|
|
 |
|
Q14.
助成金とは? |
|
 |
Q14.
条件に合致し、所定の手続をすれば必ずもらえる公的な資金であり、融資ではないので、もらったお金は自由に使っていいですし、もちろん返済する必要ありません。
財源は皆さんが納めている労働保険料の一部から成り立っているので、是非取り返しましょう。 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Q16.
助成金をもらうには何か条件があるのですか。 |
|
 |
Q16.助成金をもらうには下記のような条件があります。
■雇用保険の適用事業所であること
■労働保険料の滞納がないこと
■出勤簿、労働者名簿、賃金台帳など、いわゆる法定三帳簿を備えていること
■雇い入れ前後6ヶ月間に解雇者(退職勧奨を含む)を出していないこと
などがあります。条件が揃っていたとしても、タイミングを間違えるともらえるものももらえません。 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Q17.
私は、昭和21年4月生まれです。夫はサラリーマンです。
結婚は昭和42年9月で その時 夫は既に厚生年金に加入していました。当時、国民年金に加入しておらず 昭和61年4月からは第3号被保険者ということで保険料は納付しておりません。もうすぐ60歳になります。私は国民年金がもらえますか。 |
|
 |
Q17.
この例では以下の点がポイントとなります。
□昭和42年9月に結婚し 昭和61年1年3月まで 夫の厚生年金の加入期間である19年7ヶ月が合算対象期間(カラ期間)となる。
□昭和61年4月以降60歳になるまで、国民年金の第3号被保険者として約20年国民年金の加入期間になる。
□国民年金の必要加入期間は25年ですから、国民年金の20年間分と合算対象期間(カラ期間)の19年7ヶ月を合わせると25年以上となる。
以上のことから このケースでは 20年間分の国民年金(年間・約40万円弱)は65歳から支給されます。
旧国民年金法では サラリーマンの妻は国民年金に加入してもしなくてもよかったのです。ただし夫が厚生年金か共済組合など、国民年金以外の公的年金制度へ加入していた期間があれば、配偶者はその期間も合算対象期間(カラ期間)に算入されます。
カラ期間として合算期間の対象とされるのは、国民年金制度の施行された昭和36年4月1日以降の20歳から60歳未満の人です。
■合算対象期間(カラ期間)とは
夫の被用者年金(厚生年金・共済年金・船員保険)の加入期間を、妻の年金の資格期間に合算できるのを合算対象期間(カラ期間)といいます。なぜカラ期間というかといいますと、年金の額の計算には算入できないので、つまり年金額は空という意味からきています。また明治44年4月1日以前に生まれた人と20歳前の期間は、たとえ夫が公的年金に加入していても 合算対象期間とはなりません。離婚した場合は前夫の年金加入期間なども合算対象期間(カラ期間)扱いになります。
|
 |
|
|
|
さらに詳しく知りたい方は お気軽にお問い合わせくださいませ。
 |
|
